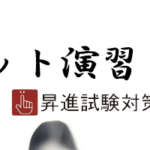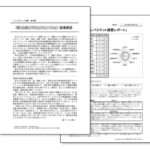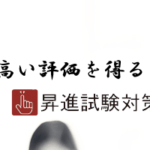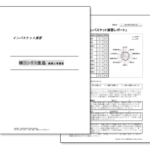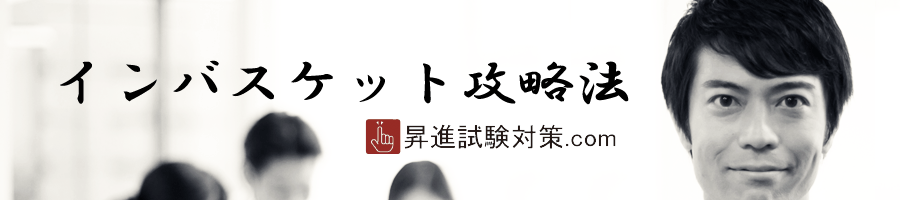
このページでは、アセッサーとして人材アセスメントを行ってきた経験やインバスケット演習の対策講座・フィードバックサービスを通じた受講者の傾向から見えてきたポイントを念頭にインバスケットの攻略法、コツ、回答方法を紹介していきます。
目次
インバスケットとは何か
インバスケットは、人材アセスメントで使用される演習の一つです。人材アセスメントは、実際の仕事に似た状況に皆さんの置くことで皆さんの行動を観察し、それを評価する手法です。
インバスケットは、管理職の書類作業を模した演習で、机の上に置かれた未決箱(インバスケット)に溜まった書類について、何かしらの行動をして既決箱(アウトバスケット)に入れていくという流れを前提に設計されています。
ですから、まず「指示書」で皆さんが置かれる状況が説明され、「案件」と呼ばれる未決書類が10~30ほど渡されます。この案件について、判断や指示の内容を「処理用紙」に書き込むことになります。 より詳しい内容は、インバスケット演習とはで更に詳しく紹介していますので、興味がある方は参考にして下さい。
インバスケット演習の例
では実際のインバスケットはどのようなものでしょうか。簡単な例題を紹介しますので、これでイメージを持っていただければと思います。
あなたは、ある製菓メーカーの本社で商品企画部係長として働いています。
この度、〇〇営業所の所長である△氏が急病による長期療養に入ることになり、新所長としてあなたに白羽の矢が立ちました。あなたはこの人事を了解し、溜まっている△氏の仕事を少しでも処理すべく、〇〇営業所に行くことにしました。
現在は午前11時、〇〇営業所で△氏の机に座っています。机には未決済の書類が積み上がっており、メールも溜まっています。あなたはこれから2週間の米国出張を控えており、本日午後1時には空港に向かって出発しなければいけません。
営業所にはあなた一人です。休日のため営業所社員に電話することはできません。また、米国出張中は営業所の従業員と連絡を取ることはできません。あなたの着任日は、●日となります。
発信:部下A
○日にゴルフコンペがあります。例年所長が参加していますが、どうしましょうか。
インバスケットの流れ
インバスケットの演習時間は、案件数によって決まることが多く、60分~180分と幅がありますが、20案件・120分が一般的です。 これだけでも大変ですが、インバスケットと並行して面接演習(準備も含めて20分程度)が行われることが一般的ですので、更に大変になります。
なお、インバスケットに取り組んだ後、6人程度のグループでグループワークを行うケースもあります。このグループワークでは、インバスケット演習を題材に指定された案件について議論し、対応策を発表させるということが一般的です。このグループワークでも皆さんの行動が評価されますので、気を抜かずに取り組んで下さい。
インバスケットの回答の書き方のコツと攻略法

それでは、具体的にインバスケットを攻略するためのコツや書き方を考えていきましょう。
読むスピードは大事
インバスケットは読むスピードを競う試験ではありませんので、所謂速読は必要ありませんが、ある一定の時間内で情報を”正確に”読み取る能力は必要となります。
インバスケットの文章量は非常に多く、参加者にかなりストレスを与えるように設計されていますので、普段から書類や本を読む習慣がなく、文章を読み取ることが苦手な人にとっては不利となることは間違いありません。
文章をスピーディかつ正確に読むためには、通勤時間やスキマ時間に新聞や本を読むことで活字に慣れることがまず必要になります。そして、読んだ内容について要旨を簡単に口に出すような訓練をすることで、より正確に文章を把握することができるようになります。
一般常識を持つ
インバスケットは、営業、生産、研究開発など様々な職種の人が一同に会して行われるものですから、公平性の観点から、知識を問うようなことはありません。しかし、回答を書こうとする場合、あまりに浮世離れしてしまう回答では良い評価は得られません。
実際の業務でも、社会の動向に疎く、一般常識がないような上司に付いていこうと思う部下はいないでしょう。
経営や財務、労務について最低限のビジネス的な一般常識は持つようにして下さい。
方針を持つ
インバスケットでは、処理にあたってマネジメント層として自分がどうしたいのかを決めることが必要です。
実際の業務に照らしてみると、マネジメント層の方針が不明瞭なグループでは、社員それぞれが好き勝手バラバラに動いてしまい、成果の獲得がままらないということは肌感覚で理解できると思います。
それとは逆に、高い成果を上げているグループではリーダーシップに優れたマネジメント層がが明確な方針を示しているということも至極明白なはずです。
優先順位を設定する
通常業務でも、仕事が沢山降りかかって困ってしまったということは誰しも経験があるかと思います。このような時、何の作戦も立てずに与えられた順番に仕事をこなしていったらどうなるでしょうか。大事な顧客に関する仕事よりも社内の些末な仕事が優先されてしまったらどうなるでしょうか。
しかも、インバスケットでは部下に指示する立場に置かれる訳です。皆さんが適切に優先順位を付けられないと組織全体に影響が及ぶことになってしまいます。
それでは、どのように優先順位を付けたら良いでしょうか。
優先順位は緊急度と優先度の二軸で付けるのが一般的に良いとされていますが、しっかりとした方針さえあれば余計なテクニックを弄さなくても優先順位は付けられると思います。
なお、緊急度と優先度で優先順位を付ける場合、何をもって重要なのか、何をもって緊急なのかということについては、意外となおざりになっている人が多いようです。 また、そもそも何のために重要度と緊急度で優先順位を付けるのかという点についても、よく分かっていない人が多いようです。つまり、多くの人が優先順位付けを目的化しているとも言えます。
まずは、なぜ優先順位を付けるのか、そしてどのような事案が重要なのか緊急なのかをマネジメントとしての立場で整理し、自身に腹落ちさせておいて下さい。
案件の関連性を押さえる
日頃から反射的に物事に反応してしまう人は要注意です。何か問題が起きている時は、その原因となる事象が必ずあります。インバスケットでは、ある案件に現象があり、別の案件に原因がある場合があります。推理小説に伏線が仕込まれていることとやや似ているかもしれません。
また、例えばデータ上は離職者が増加している、サービス残業が横行しているという関係者の話がある、人手が足りないなどの様々な問題点が点在しており、俯瞰的な視点を持たないと問題の全体像が見えない場合もあります。
気が急くのはわかりますが、最初に必ず関連する案件があるという前提でしっかりと全ての案件に目を通し、案件の関連性を把握してから、回答を書くようにして下さい。このようにすると時間がかかるように見えますが、関連する案件をまとめて処理出来る分、時間の節約につながります。
時間を守る
インバスケットでは、時間の使い方が非常に重要になります。全ての案件に回答することが目的ではありませんが、演習の性格上全ての案件を処理するように努力することも必要となるのです。
時間内で全案件に回答することを努力目標とし、読み込みの時間、回答を書く時間を厳密に決め、状況設定の余白等に書き、忘れないようにするのが良いでしょう。
そして、決めたことを厳守することが重要です。途中で決めごとを曲げてしまうと、結局自分の心地よいゾーンで処理をするだけになってしまうからです。
判断をする
マネジメント層が全く物事をジャッジできない場合、担当者は判断を待つことになり、手が空いてしまいます。決めるべきときには決めるという姿勢が重要となる訳です。勿論、保留する、何もしないという判断も時に必要でしょうが、一事が万事判断を回避するようではマネジメントは務まらないということです。
判断のプロセスは、情報収集と選択肢の列挙、判断軸の明確化、決断です。更に、人材の育成という観点から、自分で判断せず、部下に任せることもあります。
インバスケットで判断ができない人というのは、このプロセスが疎かになっている人です。これは、通常業務でも同じです。判断することが苦手、判断ミスをしてしまうという人は、多かれ少なかれこのプロセスに問題を抱えています。まずは、日常業務での自分自身の振る舞いを振り返って見て下さい。誰かに判断を丸投げしてしまっていることはありませんか?
スケジュールと組織図は手元に置く
スケジュールと組織図を常に手元に置いておき、回答の際には必ず参照しましょう。回答の際は、自分のスケジュールや組織のメンバーのスケジュールが矛盾しないようにしなくてはなりません。また、そもそもあなたの元に持ち込まれる様々な依頼がダブルブッキングの状態になっている可能性もあります。
5W3Hで具体的に実行できるレベルにまで策を練る
端的に言うと「やっておいて!」だけでは人は動かないということです。人を動かすためには、具体的な指示が必要となり、5W3Hの視点がかかせません。
念のために、5W3Hを挙げておくと、When(いつ)、Where(どこで)、Who(誰が)、Why(なぜ)、What(何を)、How(どのように)、How many(どのくらい)、How much(いくら)です。このフレームはあまりにも一般的ですが、意外と多くの人に抜けが見られます。
Whatは多いのですが、Whenが抜けていることもよくあります。また、特に多いのがHowの検討がなおざりな人です。方向性だけでは人は動けません。インバスケットを攻略するためには、自分が指示される立場に立って、行動しやすい具体的な指示を考えることが必要です。
報連相はしっかりと
インバスケットの状況設定には、一定のパターンがあります。すなわち、あなたは机で処理を行った後に離席し2週間程度音信不通状態になるという設定です。ですから、指示を行った後は、2週間程度の間、仕事を放ったらかしにしないといけなくなり、着任しないと仕事の成果を確認できなくなります。とすると、指示通りにしっかりと仕事がなされる、なされたかどうかが問題となってきます。それゆえ、指示を出した時点で、しっかりと進捗が確認できるようにしておくことが必要となります。
試験本番までにやっておきたいこと

まずは慣れる
インバスケットをはじめとした人材アセスメントの演習全般に言えることですが、1回目よりも2回目の方ができた!と言う人が多くなります。やはり、”慣れ”という要素は一定程度回答に影響するのです。この理由は、人材アセスメントでは時間的なプレッシャーが重要な要素だからです。時間的なプレッシャーに慣れることで、頭が真っ白になるよう事態が避けられ、余裕を持って取り組むことができるのです。
自分は割とプレッシャーに強いので大丈夫だと思う人がいるかもしれませんが、本番のプレッシャーは模擬試験とは全く異なるものです。筆者も何度も、インバスケット演習の最中に頭が真っ白になったという人を見ています。
従って、自宅でインバスケット演習に取り組む際は、制限時間を設定されているものよりも5分、10分程度短くし、練習の時から自分にプレッシャーをかけておくことが望ましいと言えます。このように、常にストレスの元に自分を置くことによって、本番で慌てないようにしましょう。
自分の強み・弱みを把握する
回答例付きの演習課題を買うことは、慣れるという意味で重要ですが、自分の回答の良し悪しを正確に把握することはできません。特に大きな弱点は、個別案件しかチェックすることができず、全体を通じての評価ができないということです。従って、できれば一度アセッサーのフィードバックを受けることが望ましいと言えます。訓練を受けたアセッサーしか、回答に評点を付けることはできません。
試験までの日程に応じて短期・長期でプランを立てる
単純に演習課題を解くだけではインバスケットは攻略できません。なぜならば、他の人材アセスメントの演習同様に、自身が日常的に仕事をしている中で身に染み込んだ癖は、インバスケット演習を盲目的に解くだけでは治らないからです。
例えば、深く考えずにとにかく仕事をさばく、逆に何でもかんでも情報を集めようとする、人に判断を任せて自分は逃げてしまい決断しない、というような癖は一朝一夕には矯正できません。多くの人がすぐに成果を求めますが、長期的な観点で仕事を通じて弱点を克服することに務めることも必要なのです。
復習をする
一度インバスケット演習を手にいれたら、次から次へと新しい問題を求めず、既存の演習課題を上手く使いまわすことも必要です。勿論、内容を覚えてしまうということもありますので、上記のように、制限時間をより短くして取り組んで、自分にプレッシャーを掛け続けるようにして下さい。
2回目の場合は、マイナス10分、3回目の場合はマイナス20分などすることが良い でしょう。また、既存の演習を深く分析してみることも必要です。中には、回答例やフィードバックを見て終わりの人もいますが、インバスケットの案件を振り返り、自分なりに分析することで得られることは少なくありません。
インバスケットに必要な能力と評価項

多くの方が誤解しがちなのですが、インバスケット演習では、模範解答に基づいて○×で点数を付ける訳ではありません。 ディメンションと呼ばれる評価軸で評価されるのです。
このディメンションですが、「〇〇力」のように能力という形で設計されています。人事評価でコンピテンシー評価を導入している企業もありますが、このコンピテンシーと類似したものと思えば分かりやすいかも知れません。
具体的には、例えば以下のような能力がインバスケット演習で評価されています。
- 自分の判断軸を設定できる能力
- 問題を分析し原因を特定する能力
- 時間管理能力
- PDCAを管理する能力
- 決断する能力
- 情報を素早く集め、把握する能力
- 経営資源を有効活用する能力
- 人材を育成する能力
※ディメンションは研修会社によって異なりますので、ここではわかりやすい表現に変えて書いています。
アセッサー(評価者)の役割は皆さんの回答をこの能力に紐づけて評価することなのです。そして、評価の際は、個別の案件に対する回答をそれぞれ評価するのではなく、回答全体を通じて評価されます。
ですから、皆さんは模範解答を手にした際は、○×で自分の回答をチェックしてはいけません。「管理職としてどのように振る舞うべきか」という視点で、インバスケット演習への取組姿勢や振る舞いをチェックして下さい。
インバスケット体験談

はじめてインバスケットに取り組んだ方の体験談をいただきましたので、紹介したいと思います。参考にしていただければと思います。
インバスケットを初めて取り組む人に向けて、初めてインバスケットをやった時の印象を書いておこうと思います。
他の演習とちがって、インバスケットは受験者が一堂に会して行うものでした。
当然と言えば当然ですが受験を思い出すピリピリとした雰囲気だったことを覚えています。
最初に、研修の事務局という人が指示書というものを通読します。
内容は自分がおかれた状況や役職、インバスケットのルールなど。
正直早く取り組みたくて気が急きます。
状況設定では、自分は営業所長の役割なようでした。
しかも、次の日から出張で1週間くらい誰ともコンタクトが取れないから、2時間の間でなんとかせいという状況。
今までに経験したことのないような無茶苦茶な状況に置かれて若干頭の上に?マークが付きました。
誰も頼れないというのがこれほど辛いものとは思いませんでした。
指示書を読んだ後は、案件に取り組むことになります。
その案件が18案件ありまして、1つ1つの案件の文章量も結構多く、読むのに骨が折れます。
私は、最初に全部を読んでみることにしました。何か課題みたいなことが隠されていているのかなと思ったからです。
そして、全部を読み込んだのだが、とにかく時間がかかりました。これだけで30分くらいかかったかも知れません。
どうやら、案件には関わりがありそうなものがあり、その関わりをしっかり見ようとしたのですが、ハッキリそうなのかがよく分からず、案件を見直しているうちにどんどん時間が過ぎてしまいました。
自分なりに余白に情報を整理してみましたが、大きな課題というのもなんとなく分かるのですが、情報が足りないような気がして、方向性も定まりません。
ここでもう50分位はかかってしまったように思います。
さすがに時間がないので、案件の順番ごとに解答し始めることに。
所与の解答用紙に書くことになりましたが、解答用紙は罫線が書かれているだけのただの紙でした。本当によくわからん状況です。
そして、4つほど案件をこなした時にふと気付きました。
これは到底終わらない。
ということは、優先順位をつけて、必要なやつだけ書けばいいんじゃないか?そうに違いない。
焦って今まで書いた解答を消しゴムで消し始めました。本当に焦りました。泣きそうでした。
そして、業績に関わるような本当に重要だと思う案件から書くことにしました。関連性のある案件はまとめて対応するようにしました。
紙はもうボロボロで、字も殴り書きです。心もボロボロでした。
全く読めないような解答を数枚書いたところで、ゲームオーバー。
結局、大量の案件をやり残してしまいました。
用紙を回収された後も、心臓のドキドキが収まりません。嫌な気分にもなりました。その日は夜までなかなか自分の気持が整理できませんでした。
数カ月後に結果が開示されましたが、最初のインバスケットは苦い結果となりました。
問題分析とか課題抽出の点数は良かったですが、計画性はからきし駄目でした。
確かに、読み込む時間も長過ぎたし、あれこれと考える時間も長すぎた、殆ど案件に手を付けられなかったのだから仕方ありません。
アセッサーの人には、殆ど処理できなかったことを指摘されました。
また、管理職としての能力は育っていないみたいなことを笑いながら言われてかなりムカつきましたね。
それと、自分としてはあれこれと悩んだことで時間を浪費したので、そういった意味では決断力が低いかと思ったのですが、点数は普通でした。本質的には決断力に問題があるのではないかと
今でも思っています。
私が最初にインバスケットをやってみて得られた教訓は、
・最初の情報整理に時間をかけすぎないこと。
・重要性だけでなく、緊急性も考慮した優先順位をつけること。
・具体的な指示内容を書くこと。
・あれこれと悩みすぎないで決断する。
・もう少し多く案件をこなす。
ということだと思います。他にも色々あると思うのですが、正直何が正解かよくわかりませんので、なんとも言えません。
次回は、自分なりの教訓を踏まえてインバスケットに取り組もうと思っています。